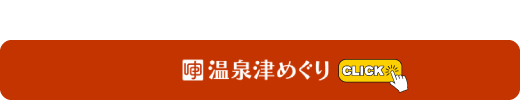【温泉津タクシー】島根県石見銀山への観光は温泉津タクシー

温泉情報

石見銀山を世界に運んだ港として栄えた温泉津は、当時の面影が残っており、現在、温泉街では初めて重要伝統的建造物群保存地区に選定された歴史ある温泉街です。
 |
■旅館街 重要伝統的建造物群保存地区に選定された温泉津温泉街から出発します。 |
 |
■沖泊(おきどまり)世界遺産 天然の港、沖泊港。石見銀山でとれた銀は、この沖泊港に輸送され沖泊港より世界に運ばれました。石見銀山が栄えた頃、船を係留するために手彫りで彫られた「鼻ぐり岩」と呼ばれる岩があります。穴のあいたものや円柱形の岩があり、縄をかけることができます。 |
 |
■やきものの里(登り窯) やさしい温もりを感じさせてくれるアメ色の陶器「温泉津焼き」。江戸時代中期に始まり、徳川時代には天領として栄え、北前船で全国に積み出されていました。温泉津に現存する登り窯は、15段30m!使用可能な登り窯としては国内最大級です。やきものの里では、焼き物創作体験が可能です。 |
 |
■石切場 温泉津には、福光石と呼ばれる全国的に有名・貴重な石が今も切り出されています。火山灰が海底で圧縮凝固されてできた軟質凝灰岩で、そのやわらかさと淡い青緑色が特徴です。古くは16世紀の頃から切り出され、石見銀山で栄えた町の住宅・造園・土木・神社仏閣等に使われていました。石見銀山の五百羅漢にも使用されています。 |
 |
■恵比須神社 社伝によれば、大永6年(1526)に建立されたと伝えられている。古くからの建物が多くのこる島根県内でもかなり古い建物とされる。 |
 |
■浅原才市像 (妙好人) 世界的に知られた昭和の浅原才市は、嘉永4年(1851)に温泉津町小浜に生まれました。温泉津で下駄をつくりながら、一万首を越える詩歌を残しています。父の死を境に求道の念が強くなり、下駄つくりの際に出るカンナ屑を紙代わりに、念仏の心をひらがなの自由詩に表現して書き留めました。 |